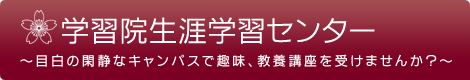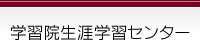山王祭
神田明神・山王権現・富岡八幡の祭礼は、江戸の三大祭と云われる。とくに神田祭と日枝神社の山王祭は、御用祭・天下祭と呼ばれている。6月15日を例祭とする日枝山王祭の起源は、比叡山の地主神から延暦寺 の守護神(山王)となった。近江坂本の日吉神社祭神「山王権現」は、天台宗の発展にともない各地に勧請された。江戸の日吉社は扇谷上杉氏の執事であった太田道潅が、戦国期の康正2年(1456)、山内上杉氏の備えとして築城した江戸城に、叡山の日吉神社の末社である武蔵無量寺の日吉山王権 現を城内に勧請したとも云われ、また天正18年(1590)家康の江戸入りに際して江戸城紅葉山に産土神として祀ったことが起源かも知れない。
その後、2代将軍秀忠の代に三宅坂上の赤坂溜池近くの松平忠房の屋敷跡(三河譜代、父忠利は深溝藩主、忠房は丹波福地山藩主を経て肥前藩主となったが、嫡子高長の代の寛文8年(1668)2月改易処分)に移転、明暦3年(1657)の大火で焼失したが、2年後に現在地へ移築された。三代家光の時代に産土神とし尊崇されたのは、将軍が山王権現を祀った江戸城内で生誕したことにようるものであろう。そのの後、明治2年(1669)山王社を「日吉神社」と改称して現在に至っいる。
この山王祭が「天下祭」とい呼ばれ、祭礼は江戸中が賑わったのは、寛永12年(1635)江戸城の櫓でこの祭りを見物し、その華美なる山車や練物の行列と勇壮な神輿を城内に招き、以後、これが恒例化したことによる。元和元年(1681)5代将軍綱吉の時、儒教主義による質素倹約により神田明神と山王権現は交互に江戸城に招聘されることになり、祭礼は隔年に現在も「表と裏」の交替で行なわれている。江戸の頃から、山王権現の氏子は江戸城から日本橋へ西から南、神田明神の氏子は東から北の地域住民となっていた。
(2006年06月07日)