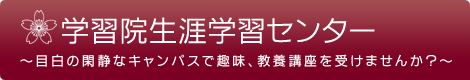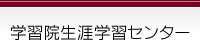花見
3月下旬から東京の桜も満開、今月の朔日(さくじつ、陰暦で毎月の第一日)の上野恩賜公園の花見客は20万人を越える人出で遅くまで賑わった。満開の桜の下での遊宴は、江戸時代でも盛んで、旧暦の3月の開花の時期には、武士も町人も酒・食べ物を重箱や茶弁当に詰め、商屋などは敷物の毛氈(もうせん) や筵(むしろ)まで持参して遊宴を楽しんだ。

当時の花見の名所は、三代将軍家光が吉野から移植した桜並木の「上野の山」、元文2年(1737)五代将軍綱吉が、「生類憐れみの令」により設置した犬の御救い小屋の跡地に八代将軍吉宗が王子の「飛鳥山」は江戸の二大名所であった。ことに、飛鳥山は江戸中心から1日の行楽のため庶民にも喜ばれた。この飛鳥山の桜植樹については、斎藤月岑の著書である『武功年表』(嘉永元年,1848)に、「元文二年飛鳥山へ桜樹を栽ゑしめらる。同所へ碑立立ち鳴鳳卿文撰す」(平凡社、東洋文庫)と記されている。
また、「向島」の桜は17世紀前半の寛永年間に、四代将軍家綱が植樹し、さらに吉宗が庶民の花見の遊宴ために増植、千住にいたるさくらなみきは大勢の花見客で賑わった。『江戸名所図絵』にも紹介されている品川の「御殿山」、家光から吉宗に至まで植樹が継続された小金井の「玉川上水沿い」、目黒の「祐天寺」境内、隅田川堤など、江戸の桜名所は多い。歴代の将軍が意欲的に桜の植樹に励んだのも、江戸城を中心に春爛漫「遊宴の楽」を願っていたのかもしれない。
このような花見は、明治14年(1881)4月6日、天皇主催の「観桜御会」として皇居吹上御苑で開催され、翌々年には浜離宮へ移り、さらに大正6年(1917)伊湖は新宿御苑で催されたが、軍国主義の台頭により昭和13年(1938)廃止され、戦後は再び「皇室園遊会」として復活している。
小澤富夫(学習院生涯学習センター講師・元玉川学園女子短期大学教授)
(2006年04月15日)