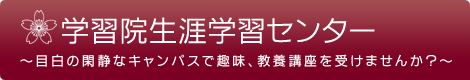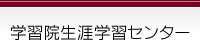雛祭(桃の節句)
古代中国の習俗には、三月最初の巳の日に「上巳の祝い」(上巳の節句)という祓いの行事があった。これは禊によって身体の穢れを払う行事で、紙や藁で作った人形に穢れを移し川や海の「形代」として流した。この人形が平安時代には貴族の子女の遊び道具となり、「雛遊び(ひいなあそび)」や「雛合わせ」が行われている。女児の玩具であった雛人形は、時代的にみると平安時代では「立ち雛」(紙雛)、室町時代では「座り雛」(人形雛)、江戸時代に入ると「雛人形」となり、ことに元禄時代(1688~1704)以後には、大奥・諸大名の奥向きや豪商の家で豪華な内裏雛、三人官女・五人囃子などの人形が段飾りされ、紅白・萌黄の三色菱形餅・霰(あられ)・白酒、桃の花・蛤(はまぐり)などが供えられた。『江戸名所図絵』には、二月中旬から下旬に十軒店の雛市の賑わいが掲載され、江戸中橋・麹町四丁目・人形町・尾張一丁目の市も雛市として知られていた。祭りの翌日には「雛流し」として飾りの段の供物を川や堀に流すのは「形代流し」の伝統をみることができる。

小澤富夫(学習院生涯学習センター講師・元玉川学園女子短期大学教授)
(2006年03月03日)