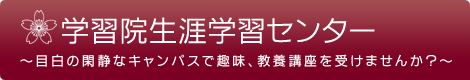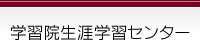「節分」
本来は四季(立春・立冬・立秋・立冬)の前日のことを言うが、とくに廿四節気が一巡した大寒の末日で、暦の年頭に当たる立春の前日を節分と称す。江戸時代にはすでに、節分の夕暮れに柊(ひいらぎ)の枝に鰯(いわし)の頭を刺し、また大蒜(にんにく)などの強烈なにおいのあるものを添えて、ものを戸口に立て邪気払いをして、大豆を煎った「鬼打豆」を撒き、その豆を食べ厄除けとする習慣があった。

こうした節分の祭は、中国古来の儀式であり、7世紀末の文部天皇の頃、宮廷の年中行事として大晦日の夜に疫病や邪気払いの儀式が行われたのが「追儺(鬼遣い、おにやらい)」である。鬼に扮した舎人(とねり)を内裏の四門に追い回し、殿上人が桃の弓葦の矢で鬼を退治した。この行事が民間の節分の行事となり、寺社で悪鬼を払う福豆を年男によって撒くことが現在もおこなわれている。
小澤富夫(元玉川学園女子短期大学教授):江戸学事始、江戸学担当講師)
ところで近年流行の「恵方巻」は、大正初期の大阪花柳界で節分の時期にお新香をまいた海苔巻きを恵方に向かって食べる風習が、昭和40年代後半の大阪で一般化したものだそうです。1989年広島のコンビニが「恵方巻」なるものを売り出し、95年には関西以西、98年には全国のコンビニで売られ広まりました。
(出典:All About社 暮らしの歳時記 節分3部作1:恵方巻(丸かぶり寿司)の謎を解明より)
(2006年02月03日)