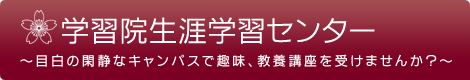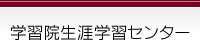「元旦の初詣」
江戸時代では、元旦早朝にその年の吉方(えほう、恵方)にあたる神社へ参詣する「吉方参り」が行われていた。この恵方は「明の方」とも呼ばれ、最徳神が訪れる方向の神社を元旦早朝に参詣し、開運札やお守りを受けてその年の福を祈願して、その帰途に初日の出を拝む習わしであった。この行事は大正の頃まで行われていた。その後、除夜から続いて元旦の初詣を行う「二年参り」が盛んになり、明治神宮や浅草寺などは大変な賑わいとなっている。

古くは、古代平安時代の宮廷の年頭行事に、正月最初の子の日に若い小松を引き抜き移植して長寿を願う「小松引き」があった。この行事は、『源氏物語』の初音の帖に、源氏が赤石の姫君を元旦に訪ねた際、庭で女の童が小松を引いて遊ぶ場面がある。
小澤富夫(元玉川学園女子短期大学教授):江戸学事始、江戸学担当講師)
(2006年01月01日)