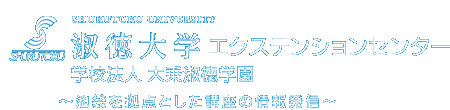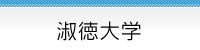ドラッカー学会の共催シンポジウム「グローバリゼーションと日本的経営の再生」が開催されました
去る12月17日の土曜日の午後1時より5時まで、恒例の淑徳大学(大学院国際経営・文化研究科)とドラッカー学会の共催シンポジウム「グローバリゼーションと日本的経営の再生」が開催されました。
当日は、まずドラッカー学会の理事の上野周雄氏から学会代表の挨拶があり、淑徳大学を代表して、淑徳大学国際コミュニケーション学部教授の岡田匡令氏の挨拶がありました。
引き続き、基調講演は、今般、『「美質」の時代』(東洋経済新報社)から出版が予定されている㈱日本香道ホールディング会長の小仲正久氏に、現況のデフレ下の中で、グローバリゼーションとローカリゼーション、さらなる展開と現状を守るために、ドラッカーの著作をどのように読むことができるかを、日本的経営や美質といった視点から、60分ご講演をいただきました。
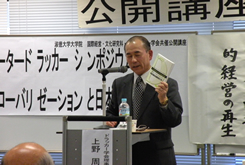 |  |
 |  |
受講生から感想や質問用紙に記入いただき、後半のシンポジウムに入りました。
まず、ドラッカー学会理事・代表代行藤島秀記氏にシンポジウムの問題提起をいただき、引き続き、シンポジウムに入りました。モデレーターの佐々木英明氏(学会理事・エクソンモービル人事統括部長)の司会進行のもとに、パネラーとして、 藤島秀記氏(ドラッカー学会理事・代表代行)、松岡幸次郎氏(淑徳大学大学院教授)、静岡で活躍している 中村克海氏(中央精工(株)取締役社長)から、多様な視点と経験からのお話がありました。
当日は、60名ほどの学会員と一般の方々の参加があり、司会の進行に従って、会場から質問もなされ、熱心な聴講風景が繰り広げられました。
 |  |
 |  |
 |  |
 |  |
2012年4月より、淑徳大学では、新たに経営学部が発足いたします。また、淑徳大学エクステンションセンター(池袋サテライト・キャンパス)も、引き続き長期的に教育機会の提供を行ってまいります。これまで、ドラッカー学会との共催講座を通じまして、学会および学会員から多大なるご支援とご協力をいただきましたこと、心よりお礼申し上げます。
【今回のドラッカーシンポジウムにご参加いただきました受講生の感想の一部を掲載いたします。】
- 現在、日本の製造現場に海外の労働者の人々がパート従業員として多く就労しています。日本の習慣(衛生面や時間管理等)の上に成り立った日本の経営において、多くの問題がでてきています。企業経営として、どのような点に努力していけばよいのが、思案しています。
- 日本香堂が日本的商品を本業とされている中で、海外展開、生産工場を移す決断の背景を深く知る機会があればと存じます。単純に価格(原油)目的での進出ではなかったのではないだろうか?この当りに関心があって聴講致しました。
- デルタ航空のお話で、成田空港をHubとしてアジア各地へ乗り入れているというお話は、日本を相手にしていないということで、ちょっとショッキングでした。しかし、日本人の1分もくるいなく到着する飛行機や電車が、海外からみたら大変魅力的というお話に関しては、今後いかしていきたいと思います。
- 「強みの上に強みを築け」とはまさに金言。しかし、日本の強みは何と考えますか?小仲会長のお話は、ざっくばらんななかにも、的を得た講演だと思いました。国内の延長に世界が有る、と言うことでしょうか!?
- 「美質」とは、とても良いテーマでした。日本の伝統と文化を大切にすることは、日本人のこれからの世代にとって重要なことであると再認識するところです。
- 小仲さんが指摘されていたように日本特有の文化(おもてなし)や日本人の持つきめ細やかさといった他国が有していない強みを生かせれば、まだまだ日本はグローバル世界で戦っていけると思います。
製品ではなくて日本が持つ文化・精神をメイドインジャパンとして世界に向けて発信することが日本再生につながるのではないかと期待できるのではないでしょうか。 - グローバリゼーションが単なる「自由化」ではなく、各国の個性、国色をいかしていくものであるということが、全体の繁栄につながるのではないかと思います。「美質」な日本を売りにして、アジアのみでなく世界へ、日本の持つ良さを売りにすることで、国や企業の強みとしていける時代を望みます。
- 小仲様の講演を聞き、刺激を受けました。内向きの志向の現在の若者、そして社会人(ベトナムへ転勤をいやがる社員)にも問題山積ですが、先人の知恵と経験をどう伝えていくのかが課題だと感じます。ドラッカー学会での研修結果を民間企業がどう活用するのか?ここに肝があると思います。
- 物事を常に両面から視る必要性をあらためて認識させられました。表と裏、はなやかな面だけにとらわれることなく、内面(裏)にも目を向けて推量することが大事であると思います。「グローバリゼーション」、それは全ての人との関わり方、顧客(人)とどのように向きあっていくべきかを常に考えて行動していくことが重要と思います。
- 「グローバリゼーション」は、日本企業が海外へ進出することだと思っていました。しかし、本日の小仲さんのお話を伺い、国内の事にも注目すべきなのだと考え方が変化しました。基本的には、人間として相手を尊重し、認め、共存し合うことが大切であることを実感しました。
- 日本香堂は、教育に力をいれていらっしゃるとのことでしたが、具体的にどのように取り組んでいらっしゃるか、教育の考え方についてうかがいたい思いで出席いたしました。日本の良さを活かしながらグローバリゼーションを進めるうえで、人材ビジネス(教育・研修・派遣)の今後をどのように見ていらっしゃるかうかがいたいからです。
- 私は日本に進出したばかりの外資系企業に勤めていますが、効率化に重点を置いた経営を求められる為に要員も充分に確保出来ず、日本独特な品質を担保する為の時間にも限度があります。一方、給与は他の同業他社よりも優遇されています。要員を多く採用するためには、給与制度そのものも日本のようにあるべきなのかと考えることが多いのです。
- 本日の小仲会長の講演を聴かせていただき思った事。ここ10年位の間に、国際化がグローバル化だというかけ声で日本企業は海外売上比率を増していったが、最近よく〝真のグローバル化〝などという言葉があちらこちらで耳にするようになりました。今までグローバルは何だったのか。真のグローバルに必要なことが少し見えてきたように思えます。日本のあるべき将来像、日本人が永遠に持ちつづけるべき価値観として、しっかりコンセンサスをとり、教育の中にくみこまないと、日本はだめになっていくような気がします。そうならないために、我々はどう行動すべきだろうか。
- 中小企業に於いて、海外進出は、言語の面のみならず、費用に於いても、リスクに於いても、なかなか踏み出せないと思います。特にメーカーの場合、生産体制を確立しても、時代の変化への対応について、量産性のあるものなら良いが、多品種の場合、段取り替えなど工夫が必要になってくるのではないかという懸念があります。小仲会長(日本香堂ホールディングス)が「ローカル」が「グローバリゼーション」の煽りを受けると言われていましたが、確かにそう思いますので、海外に生産拠点を構える注意点があれば教えて欲しいと思います。
- 日本人経営者から見た海外進出時の考え方だけでなく、欧米人から見た日本人経営者、労働者の比較も必要だと思います。World wideで競争力を持つ日本企業が少ないのは何故か、日本企業はどこまで大きくしたら成功、Happyなのか、という考え(ゴールビジョン)という視点から、今後どうするかを考えたほうが良いのでは?どこかにWASP>Japan>Asia.Hispanicの意識がないか?時間軸が加速的に短くなっているので、50年というスパンでは測りきれない多様な面があると思います。
- 本日のテーマの解決策は、簡単には見い出せないのが現状なのかもしれない。小仲さんがおっしゃったように、ドラッカーの理論は儲ける事とコントロールすることの両価的側面がある事に着目すべきだと思いました。資本主義の限界が差し迫ったら、次の展開はどうすべきか。私は世界的にスタンダードとされる価値観と日本の価値観を折衷し、中庸的な立ち位置に属することが、新しい日本的経営の再建であると思います。グローバリゼーションの観点に立つと、日本は有機的な独立的スタンスを確立できると考えます。
(2012年01月13日)