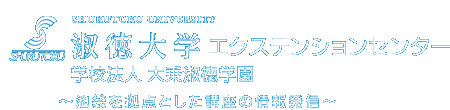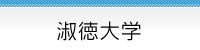「シンポジウム 総括 日本近代文学にとって東アジアとは何であったか」
淑徳大学公開講座
「シンポジウム 総括 日本近代文学にとって東アジアとは何であったか」
報告 淑徳大学エクステンションセンター 岡本勝人
さる9月10日、池袋にある淑徳大学サテライト・キャンパスにて、淑徳大学エクステンションセンター主催、日本ペンクラブ後援による公開講座「総括 日本近代文学にとって東アジアとは何であったか」が開催されました。
基調講演 I は、筑波大学名誉教授の平岡敏夫氏より、「戦記文学と東アジアの問題」について、資料により、説明がありました。平岡氏は、日本近代文学会の重鎮であり、現在も顧問をしておられます。
内容は、日清戦争における正岡子規の「陣中日記」や国木田独歩の「愛弟通信」、日露戦争における森鴎外の「うた日記」や桜井忠温の「肉段」、第一次大戦における「青島戦記」、その後のノモンハン戦争から日中戦争、太平洋戦争における「昭和十五年の無名戦記 十冊」や大岡昇平の「レイテ戦記3」などについて、軍国少年であったことの原点からご自身がこれまで書いてきた膨大な研究成果を含めて、戦争の悲惨さにたいする戦後の文学研究の立場からお話がありました。
次に、基調講演 II として、法政大学教授で文芸評論家の川村湊氏より、「現代文学のなかの東アジア」と題して、ご講演がありました。川村氏は、日本の旧植民地下文学についての編著書が多く、集英社の「コレクション 戦争と文学 全20巻」の編集委員もされています。
内容は、基調講演Ⅰを踏まえて、戦後文学の評価から脱イデオロギー的な視点により、東アジア文化圏のなかでの戦後から現代の日本人の作家、大岡昇平から津島祐子、村上春樹までの作品が紹介されました。ここには、明らかに戦後文学や戦後史からの視点の転換があり、現在の東アジア共同体論や竹島や尖閣列島などの政治的問題が顕在化する東アジアという時代的思考にかかわるものでした。
以上の二つの講演に基づき、各参加者から質問や感想などを聴取し、後半のシンポジウムに臨みました。
シンポジウムは、文芸評論家で先頃鮎川信夫賞を受賞した司会の神山睦美氏により、ゲストである学習院大学教授の兵藤裕己氏に最初にお話を伺いました。兵藤氏は、ふたつの基調講演とは異なった、日本人の中世以来培われ、通底する庶民大衆の原像に視点を当てる論点によって、日本近代における日本人にとっての戦争と文学について、発表をいただきました。
主な感想と意見には、中国の現状と日中友好に関する質問や明治以降戦中に至るアジア主義者の存在についての意見、孫文や日中を往還した文学者や竹内好の評価、日本近代文学としての「戦記物」以外の東アジアという視点や観念を持って描かれた、例えば金子光晴などの小説作品や詩作品に関する質問、ヨーロッパから発生した1920年代のモダニズム運動の芸術運動にとって、東アジアとはどんな位置にあったか、また、樋口一葉の師の半井桃水が朝鮮文学に造詣が深いように、中国文化や文学の日本近代文学への影響という視点で、いかに日本的と言える発想が成立したかという質問。
中上健次の熊野三部作にでてくるアジアのイメージや『異族』のアジアへの眼差しや問題意識は、現代の日本と東アジアの文学や思想を先駆ける予見性があったのではないかという意見、東アジアでの戦争後の各国の文字表記の変化についての質問などがありました。
神山睦美氏より、長年、わたしたちの思考の方向が、ヨーロッパ中心であったこと、戦後の歴史観や文学観によるアポリア(難問)が前提としてあり、魯迅と東アジアという視点や日本近代の時間を超えるパースペクティブを持つ必要性などが語られました。
今日の東アジアをめぐる問題が露出する現代の日本にとって、今回のシンポジウムは、日本近代文学にとっての東アジアとは何であったかを総括し討論することで、難問としての東アジア問題の行く末を語っていただきました。経済社会的に先行するグローバリズムの中で、地勢的なテーマとなりつつある東アジアの問題は、今後、環太平洋の経済流通も視野に入れながら、大きな論点とされるだろう。 2011.9.26
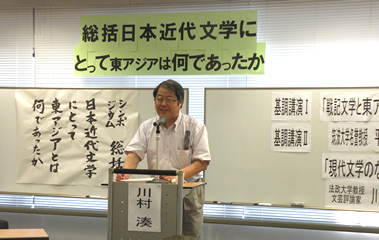

(2011年10月12日)