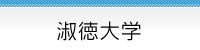「秋の気配」 岡野絵里子
「さわさわとやってきた秋にのって/ニセアカシアの道を歩いて行きなさい/仕立屋さんが大きすぎる/上着を直してくれる」
山本楡美子さんの詩「午後の一部」は、さわやかな十月の風の訪れで始まる。ニセアカシアの並木道がまっすぐに伸び、どこまでも歩いて行きたくなる季節。長かった暑い夏を通り抜けて、私たちは新しく生まれ変わったような気持ちになっている。だから新しい上着がいるのだ。
上着にコート、マフラーと厚着をしていく人間と反対に、樹たちは葉を落としていく。ニセアカシアは落葉樹。東京には意外に街路樹は多くて、銀杏やプラタナス、ハナミズキなどが目に親しい。都会の固い地面や排気ガスに耐えて、緑陰を提供してくれる梢が秋からは、風をよく通すようになる。
「ニセアカシアの道は公園へ続く/森に着けば/前夜の匂いがするだろう/ニセアカシアにこそ上着をかけてやりなさい/誰もいなくなった後も/あなたの唇のように/震えている」
前日に何か催しがあったのだろう。人が賑わった気配が濃厚に残っている公園。秋風に震える枝が、言葉を出せずに震える人のように儚げで愛おしい。詩人にとっては、樹木と人が区別なく大切な存在なのだ。山本さんの中にも、一本の美しい楡の木が世界を見つめながら立っている。
岡野絵里子(詩人・淑徳大学公開講座「詩人の童話を読む」担当)
(2011年01月14日)