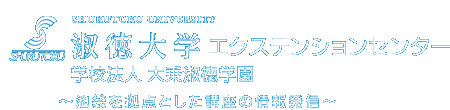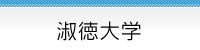エッセイを書く(9)
戦前の小学生時代の暮らし
氣多 保雄さん
私は小学生時代、広島市の郊外、海辺近くの、周囲一面蓮根畑の真ん中で暮らしていた。満潮になると、海面より低くなったと思われるような低地だったので、さぞかし土地は手に入れやすかったのか、周囲五軒、みんな広い敷地に、各種果物の樹に囲まれて住んでいた。退役軍人が三軒、画家一軒、退職した校長一軒が隣組で、夫々功成り名とげた(?)方々の隠居屋敷だった。また一分ほど離れて大邸宅があり、アメリカ帰りの成功者一家が住んでいた。
私は、父が定期的に転勤する職業(海軍技術士官)のせいか、母の実家に預けられ、母の兄弟姉妹三人と一緒に通学していた。私は大西洋戦争開始時期の、昭和十六年三月に小学校卒業なので、それ以前の三年位の平和な時代の暮らしの記憶を懐かしんでみたいと思う(実際には既に中国大陸では日支事変、欧州では第二次大戦中だったが、小学生には身近な感じではなかった)。
三キロほど離れた学校から帰ると、内玄関の隣の女中部屋にカバンを投げ入れ、外に飛び出しいつもの悪餓鬼達と集い、鬼ゴッコ、トンボ取り、空気銃で雀撃ち、メンコ取り、コマ回し、竹馬、縄跳び、軍艦ゴッコ等々、暗くなるまで走り回っていて、誰かの親に叱られながら帰宅する日課だった。
休日には、飴をしゃぶりながら紙芝居の後をついて廻ったり、ポン菓子屋をつけまわしたり、海べりのかき貝の工場に入り込み、おばさん達から採りたてのかきを口に入れてもらったり、堤防や橋の欄干から飛び込んだり、ちょっと歩いて小山に分け入り、松茸、ハツ茸を採ったり、とにかく、野山、海、川を走り回っていた。また、時には祖父のお供で猟犬とともに鴨撃ちに行ったり、釣り舟を出して黒鯛(ちぬ)、鯛、ふぐ、きす、かれい、かわはぎ等々の釣りに行ったりしたものだ。今考えてみると、なにかとても優雅だったように思う。
当時は、一般家庭にテレビはない、電話もない。ラジオと新聞が情報源。水道はあったがガスはない。勿論、車はない。炊飯器、洗濯機、掃除機もない。従って、祖父の車は馬であり、世話する馬丁の兵隊さんがいたし、ご飯炊き、洗濯婦、掃除婦など女中さん達がいた訳で、多少贅沢かとも思うが、決してすごく贅沢ではなかった。というのは、明治以来我が国は富国強兵で、産めよ増やせよと、まずどの家でも子沢山、特に農漁村は子沢山だったので、口減らしか(?)、衣食住を与えてくれればと、そして行儀見習いとして是非、とむしろ頼まれて預かった娘さん達だった訳である。ちなみに、私の父の兄弟はなんと九人、母は五人だった。祖母はその娘さん達に行儀を教え、裁縫を教え、ある年齢が来たら嫁入り道具をつけて、お嫁入りの面倒をみていた。行ったらいや、と泣いて引き止めた記憶がある。
ここで、当時、日常生活物資はどうしていたのか、思い出してみよう。
現今のように、コンビニなどは勿論、スーパーもない。まして中心部より数キロ離れた蓮根畑の中、お店など全くないのに殆んど不自由はないのである。どうして?……それはお店の御用聞きが、注文取りにせっせと通ってくるからなのだ。一番に思い出すのは、重箱を浅くして横に引き伸ばした箱に、沢山の仕切りをして、駄菓子のサンプルを並べて注文をとるおじさんのことだ。たまたま家にいるときは、祖母からの呼び声で台所に飛んでいったものだ。また、京都の和服屋、染物屋が見本をかついで来た時は、子供なのにどうしたことか見本を見るのが大好きで、祖母から意見を聞かれ懸命に批評をしたものだ。また富山から定期的に薬売りが来て、私にとお土産の菓子をくれたりして嬉しかった。
その他、毎日のように魚売り、かき売り、八百屋、トーフ屋、酒屋、米屋、パン屋(主として蒸しパン)、薪炭屋、小間物屋等が、夫々掛け声、鈴、ラッパで廻ってきたのである。案外今より便利だったかもしれないと思う。なお、文房具は、ちょっとした物は学校の売店で、特別なものはデパート(確か二軒あった)か、「本通り」という繁華街の店で求めた。
当時は、外食産業は今のように発達しておらず、年に二、三回、デパートの大食堂で洋食を頂くのがおおご馳走であり、給食は勿論ないのでアルミの弁当箱持参で、冬はなんとスチーム暖房の上で温めて食べたものだ。当時、このスチーム暖房は最先端だった。なお果物は、自宅の敷地内の五本の柿、びわ、いちじく、ざくろ、苺で随分重宝した。残念なことに、広島名産のみかんがなかったのは不思議だが、多分育てるのが難しかったのだろう。栗は、十分ぐらい奥の山に行けば転がっていたし、リンゴは祖父の知人から毎年どさっと送られてきた。
そして、正月をはじめ、ひな祭り、お節句、その他毎年の定期的行事には、お客を招いて祝ったものだ。その都度、ちらし寿司が必ず出た。
直ぐ上の兄さん(実際は母の末弟)が、中学生なのにハイカラで、天火と称する鉄板の箱で、上と下に炭火を置いて、苦心惨憺、なんと、見事なシュークリームを作ったのにはびっくりした。
(この兄さんには特別の思い入れがあるので、しばし脱線をお許しあれ。中学時代独学で、ピアノ、バイオリンをマスターして、学芸会で独演していた。小生には、なんとかして上野の音楽学校に進みたいと言っていたが、四囲の環境、とても言い出せず、教師の強請により泣く泣く海軍兵学校に入り、果ては、とうとう神風特別攻撃隊の隊長として、七人の部下と共に、終戦の年の春、米航空母艦に突っ込んで戦死してしまった。残念無念慙愧のきわみであり、いつかこの経緯を詳しく書いてみたいと思っている。)
(2008年08月04日)