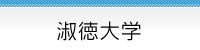エッセイを書く(8)
初恋――ゆめのまた夢
氣多 保雄さん
序段
エッセイを書こうと集う仲間のご婦人が、「最初の記憶」と題する興味深い一文を披露された。ふっと、「記憶」を「恋」におきかえたら、さぞかし愉しいエッセイが拝見できそうに思い、口に出してしまった。なんとその時は、自分にも宿題となることを失念していた。イヤハヤ。
とにかく半世紀以上も前の、とぼしい青春時代の漠然とした記憶をたどり……心にうつりゆくよしなし事を、そこはかとなく書きつくれば、あやしうこそものぐるほしけれ。
第一段
それはどんよりと低く垂れ込めた雨雲の下、場所は東京駅八重州口の切符売り場の長い行列のなかほどに、うんざりと居たときである。時は終戦まぢか、昭和二十年(一九四五年)、四月初めの午後。自分は旧制中学を卒業して進学も決まり、その入学式の前に、祖父母と住む広島から鎌倉に住む父に会いに行き、そこからさらに常陸太田に疎開していた母と弟に会いに行った帰り道のことであった。
「学生さん、どちらまで行くの?」と話しかけてきた前の婦人にびっくりして見ると、自分より一回り以上は上と思われる妙齢の婦人であった。なんと、当時のご婦人は、殆んどもんぺと称する地味なズボンまがいに、背中に防空ズキンといったいでたちであるのに、かの女性は、見事な花模様の着物姿ではないか。それにしては似つかわしくない、大きな重そうな革のトランクを持っていた。とにかく二人とも、夕方発の下り急行に乗る目的だということがわかった。
窓口で、当日は満員であるとことわられ、翌日の切符を買わされてしまった。当時は、むしろ翌日のでも買えたことを良しとする状況で、ご婦人(以下、T女とする)は実家の埼玉へ、自分は鎌倉で一晩過ごし、翌日ホームで再会することになった。
しかし、T女の姿に似つかわしくない、重いトランクが気になり、つい持ちましょうと、ホームまでの長い地下道と階段を赤帽して(註1)、大宮行きの電車を見送ったのであった。ホームより南、江東方面は前月の大空襲で惨憺たる焼け野原であり、いまだその匂いがたちこめていたことを思い出す。
(註1)当時有料で手荷物を運ぶ駅員は、赤い帽子をかぶっていたので赤帽と呼ばれた。
第二段
翌日夕刻、東海道線下り急行ホームは、老若男女で溢れかえらんばかり。T女はその中で一目でわかる着物とトランク、再会は簡単である。やがて列車が到着すると、身軽な自分はいち早く座席を確保して、並んで腰掛ける。さあ、それから、身の上話が延々と夜半まで続くことになった。
実家は埼玉の旧家で、父上は早稲田の教授であり、本人も大学で何と哲学を勉強したこと、父上が勝手に決めた教え子で、近江の旧家の息子と結婚して、一男一女をもうけたこと、その夫君は招集で南方へ行きあっというまに戦死してしまい、地主として広い田畑をかかえ、小作人がいるとはいえ、姑と二人でどうしようかと思い悩んでいること等々、持ち前のおせっかいでも自分には如何ともしがたいT女の境遇ではある。夜半、静岡を過ぎたころまではどうやらつきあったが、睡魔には抗し難く、ウトウトと座ったまま寝てしまったらしい。何時間たっただろうか、ハッと気がつくと上体が横になり、T女の膝に頭が乗り、右手が膝の上で強く握り締められており、その上にショールが掛けられて視界からさえぎられているではないか。なんとも、はずかしいというか、暖かく気持ちいいというか、身動きができずじっとしていた。
第三段
……まもなく大津――大津―…との夜明け車内放送をきっかけに、初めて目覚めたさまをよそおい、照れ隠しに大きな背伸びをしながら
「あれ、もう大津。おはようございます。Tさん、そういえば米原でおりて電鉄(義父が創られたとのこと)に乗り換えると言っておられたのに」
「あなたが熟睡していて起こすのがしのび難かったからよ。終点の大阪までつきあうことにしたわ」
「いやあ、申し訳ありません。なら、すぐ山陽線に乗り継がないで、半日道頓堀でも歩いてみましょうか。神戸の叔母宅か甲子園の叔父宅に今晩泊めてもらって、明日広島に帰ることにしてもかまいません」
「そうしましょう。私も道頓堀は久しぶり。嬉しいわ」
大阪駅で荷物を預け、地下鉄で道頓堀に出た。戦時色真っ盛りの道頓堀をどのように歩いたのか、殆んど記憶がない。ただ、味の薄いうどんの昼食を、二人で顔を見合わせながら懸命にすすったことを思い出す。よそ目に二人はどう映ったことだろう。きっと、何処かの学校に進学する弟を見送る姉ぐらいに見えたのではないか。しかし自分にとっては、生まれて初めての嬉しいような愉しいような数時間であった。あちらこちらで敵機の空襲にさらされながらのそれまでの殺伐とした日々を、一刻忘れる時間を過ごした。
しかし、T女の二人のおさなごは母親の帰りをさぞかし待っているだろうし、自分もこのような時間をもったまま叔父や叔母に会う気持ちにはなれなくて、思い切って午後早めの汽車で右左に別れることにした。もし機会を得たら、再会を約束して。
自分の汽車が先だったので、改札口でさよならして入ったら、「あっ、忘れ物」と呼ぶ声で呼び止められ、柵の向こう側で彼女が手招きしている。何だろうと柵まで引き返したら、いきなり首に腕が巻きついてきて、猛烈な接吻をされたのである。思わず顔が真っ赤になり、無言で階段を駆け上がった。何しろ小説その他で接吻に興味を持ってはいたが、この時期に自分が体験するなど思いもよらず、平常心に戻るまで何時間もかかったような気がする。突然で、しかも受動的なもので、味わうどころではなかったが、何か成熟した女性の味は、匂いは、あんなものかと真っ赤な顔のまま考えていたような気がする。
第四段
無事入学式も済み、戦時即席技術者育成の為の詰め込み教育が始まった。
高等数学、物理、電気磁気学、ドイツ語等々よく解からぬままどんどん先へ進んでいき、食傷していた矢先、祖母から「この人だれ?」と、ぶあつい封筒を渡された。裏を返したら、T女の署名が墨痕あざやかに記されていた。
「この前汽車で知り合った近江の小母さんで、握り飯等をもらって有り難かった」
と説明し、少々あわてて自室に急いだ。多分祖母は、うのみにはしなかっただろう。急いで開封すると、何と和紙の巻紙に、さらさらと見事な墨の字が延々と書き連ねてあった。内容は、大阪で別れてからの日常の出来事を、日記ふうに淡々と詳しくしたためてあった。多分、家人の目にふれることを意識して、深遠な配慮がされているのだと思った。同居の祖父が人一倍厳格な人だということを、大阪で話したからだろう。
だが行間には、僕だけに判るあの猛烈な体験の延長が見受けられ、懐かしいというか驚いたというか、多少困惑のうちにも嬉しいというか、なんとも表現しがたい気持ちで、何回読み返したことだったろう。いにしえの女流歌人がしたためた手紙もかくやあらんと思われる名文と達筆に、しみじみ感心し、強烈な印象を受けた。
第五段
それからというものは、三日にあげずよくも書くことが有るものだと、日記が届くことになった。五通に一回程度は自分も下手な字と文章で返事を書いたが、今考えると、誤字脱字の羅列の、名文ならぬ迷文だったと思う。学校の都合で九歳より祖父母に預けられた自分は、潜在的に母の愛情を求めていたのだろうか。擬似母としての、否、姉としての、いやこれも違う、初めての恋人としてかもしれぬ女人に、とにかく懸命に返書をしたためた。
その往復書簡が約三ヶ月続いているうちに段々高揚してきて、何とか機会を作って再会しようということになった。とにかく戦時下、そう簡単な事ではない。幸い、学期末に一週間ほど休暇となり、その後、学徒動員として電力会社に派遣されることになった。祖父母には、父母に会いに行くというまたとない口実ができたので、早速連絡をとり、思い出の大阪駅の改札で再会する約束をした。
三ヶ月前に時計が逆戻りして、それからどうなるか成り行き次第と覚悟して、夜行列車に飛び乗ったことである。
翌月にはあの「ピカドン」にあい、生死のさかいをさまようことになろうとはつゆしらぬ、お目出度い自分の、胸ふくらませた初恋の旅路ではあった。
(2008年08月01日)