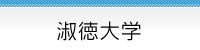小説創作講座(4)
少女の唄
高松恵里佳さん
あの人は私に何をくれたんだろう。
私は何を与えたんだろう。
あれから四ヶ月が過ぎていた。日常の自分を囲む風景画はいつもと同じ色だ。
学校の窓の縁はいつものように汚れている。世界史の先生はあいかわらず声が小さい。窓側の私の席からは体育館に続く石段が見える。
あてもなく、石段を数えては、授業から意識を飛ばした。20、21、22……、そしてやはり、意識はあの日へと流れてゆく。
あの夜を、数字に直していこう。
この世にあるもので数字に直せないものはないと誰かがテレビで言っていた。
ひと晩いっしょにいて、キスは2回。
手をつないだのは1回。
私は手をつなぎたいと夜道を歩いているときから数えて、5回思う。
朝方、あの人はキャスターマイルドを2本吸った。
私の名前を、あの人は1度も呼ばなかった。
体の痛みよりも心の痛みを何度も感じた。だけど、私はしらんぷりした。本当は全部わかってたんだ。
処女と童貞の夜。
そういえば夜中の一時に一度だけ、彼は私のことを好きだといった。そんな気持ちが偽物に限りなく近かったのはわかっていた。ただ、私の中のワタシが、痛い、痛いと泣いては錯覚させた。しかし彼だけが悪いわけじゃない。お互いが加害者で被害者だ。
自分の視界に覆い被さるように上にいる彼の体を凝視したとき、うっすらと、ある疑問が浮かんだ。
この体はなんだろう。赤の他人の体にしか見えない。私が恋こがれたあの人はこの人だったのだろうかと。彼も私のことを心の底から好きではないだろう、だとしたら、今やっているこれはなんだろう。
それでも私は彼を手にいれたいと強く願った。しかしあの夜以来彼の声のかけらすら、聞くことは私に与えられなかった。
終了のチャイムが鳴ると同時に、みんなが慌ただしくしゃべり始める。私も友達の席へいきかけたが、それをやめ、すぐに帰ろうと思い直した。教室を出ようとしたとき、後ろで友達の声が聞こえた。
「さや、部活でないのー」
「あー、先生に頭痛がするから帰るっていっといて」と振り向き、返した。
「ずる休みだっ。また先生キレるよー」と、にたにた笑いながらジャージを振り回し叫ぶ友に笑顔を返し教室を出る。
家までの帰り道、朝方降った雨でできた水たまりをよけながら下を向いて帰った。
太陽は湿った空気をかわかすかのように照り輝いている。傘で水たまりをつつきながら私は考える。
決死の思いで一目惚れしたと手紙に書いた今の私の気持ちを、大人になった私は忘れてしまうのだろうか。そして、あの人の気持ちを少しは理解できるんだろうか。
急な坂道にさしかかると私は空を見上げた。
太陽の光が頑張れとも言わず、よくあることだよとも言わず、ただ、ただ、私を照らした。
だから私は少し上向きかげんで歩いた。 (未発表)
(2008年07月22日)